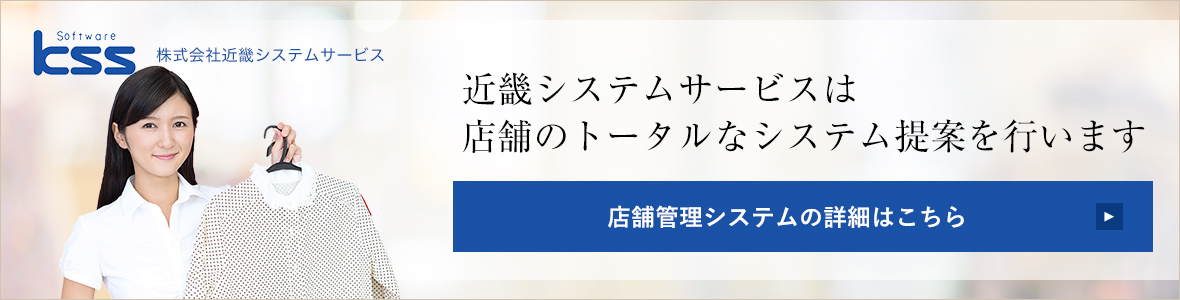企業の売上管理や在庫・仕入れの効率化において、クラウド型販売管理システムの導入が加速しています。
この記事では、クラウド型販売管理システムの基本的な仕組みや主な機能、導入メリットや注意点についてわかりやすくご紹介します。
目次
クラウド型販売管理システムとは?
クラウド型販売管理システムとは、販売(売り上げ)や在庫、仕入れなどの業務をインターネット経由で一元的に管理できるシステムのことです。自社サーバーを使わず、クラウド環境上で稼働するため、場所を選ばず利用できる点が特徴です。
クラウド型とオンプレミス型の違い
販売管理システムには、大きく分けて「クラウド型」と「オンプレミス型」の2つの種類があります。
クラウド型がインターネット上のサーバーを利用し、ベンダーが提供するサービスを通じて販売管理業務を行うのに対して、オンプレミス型は、自社内にサーバーを設置し、システムの構築・運用・保守をすべて社内で行う方式です。
それぞれの方式には、次のようなメリットとデメリットがあります。
| 種類 | メリット | デメリット |
| クラウド型 | ・初期費用が安く、短期間で導入できる
・インターネット環境があればどこでも利用可能 ・ベンダーによる保守で運用負担が軽い |
・カスタマイズ性が低い
・通信障害や災害時に利用できなくなる恐れがある ・継続的な月額費用が発生する |
| オンプレミス型 | ・自社業務に合わせて柔軟にカスタマイズできる
・オフラインでも利用できる ・セキュリティや運用管理を自社でコントロールできる |
・導入費用が高く、構築に時間がかかる
・社内に運用・保守体制が必要 ・アップデート対応が手間になることがある |
クラウド型はコストと運用面での負担軽減に優れ、特に中小企業やスモールスタートに適しています。一方で、オンプレミス型は業務に合わせた柔軟なカスタマイズや、セキュリティを自社で徹底管理したい企業に適しています。
クラウド型とオンプレミス型の違いをさらに知りたい方は、以下の関連記事も参考にご覧ください。
>>クラウドとオンプレの違いとは?【コストやメリットを比較】
クラウド型販売管理システムの機能

ここでは、クラウド型販売管理システムが備える主な機能について解説します。多くのクラウド型システムでは、販売・在庫・購買の3つの管理機能が中心となっています。
販売管理機能
販売管理機能では、受注から納品・請求・入金までの流れを自動化し、一元管理できます。顧客ごとの取引履歴や売上分析、売上予測なども可能で、販売戦略の最適化に役立ちます。
例えば、売上分析機能を活用することで、売れ筋商品や販売チャネルごとのパフォーマンスを視覚化し、意思決定を迅速に行えます。
在庫管理機能
在庫管理機能では、商品の入出庫・棚卸し・在庫数のリアルタイム把握が可能で、現場の在庫状況を常に最新の状態に保てます。これにより、現場担当者は都度確認の手間を省け、在庫の偏りやロスに対応可能です。欠品による販売機会の損失も防げます。
購買管理機能
購買管理機能では、仕入れ先との発注・納品・支払管理を一括で処理できます。適正在庫数に応じた発注提案や仕入れコストの見える化により、無駄なコスト削減や取引先の選定精度が向上します。
クラウド型販売管理システムを取り入れるメリット
クラウド型システムには、多くの企業が魅力を感じる利点が数多く存在します。ここでは代表的な4つのメリットについて説明します。
業務効率がアップする
販売・在庫・仕入れ業務を一元管理できるため、部門間での情報共有がスムーズになり、データの二重入力や手作業による伝票処理、Excel集計などの非効率な業務を大幅に削減できます。
例えば、受注情報が即座に在庫システムに反映されることで、在庫引当や出荷指示がリアルタイムで連動し、タイムロスや伝達ミスを防ぎます。さらに、統一されたデータベースにより、部署ごとの数字のズレや確認作業の手間が省け、経営判断のスピードも向上します。
人為的なミスを防げる
手作業による入力ミスや伝票の紛失などを防げる点も大きなメリットです。
紙やExcelによる記録は転記や集計時にミスが発生しやすく、数量ミスや請求漏れといったトラブルの原因になります。クラウド型システムでは受注データや在庫状況が自動的にシステム間で連携されるため、こうした人為的ミスを大幅に削減できます。
さらに、担当者間でリアルタイムに情報が共有されるため、二重発注や過剰在庫といった問題の未然防止にもつながります。これにより、業務の信頼性と顧客満足度の向上が期待できます。
販売管理の導入・運用コストが低い
クラウド型は初期費用が低く、月額利用料などの定額制で利用できるため、予算計画が立てやすいというメリットがあります。
サーバー機器やインフラの構築が不要なため、初期投資を抑えながらも本格的な販売管理機能を活用でき、資金に限りのある中小企業やスタートアップ企業にとっては大きな利点となります。
また、システム運用にかかる人件費や保守費用も不要なため、トータルコストでも非常に効率的です。
インターネット環境があればどこでも利用できる
インターネットさえあれば、外出先・リモートワーク中でもPCやスマートフォン、タブレットからクラウド型販売管理システムにアクセスすることができます。
例えば、営業担当者が顧客先でその場で在庫確認や受注入力を行い、リアルタイムで社内チームと情報を共有することで、スピーディな手配や出荷指示が可能になります。
また、複数店舗を運営している企業では、各拠点の売上や在庫状況を本部が即座に把握できるため、迅速な戦略判断にもつながります。
クラウド型販売管理システムを導入する際の注意点

メリットの多いクラウド型システムですが、導入に際してはデメリットやリスクも理解しておく必要があります。
カスタマイズの自由度は低め
クラウド型は基本的に標準機能でパッケージされており、短期間で導入しやすい一方で、個別の業務プロセスに合わせたカスタマイズなど柔軟性には限界があります。
例えば、特殊な在庫管理ルールや独自の売上処理フロー、帳票出力フォーマットなどがある場合、標準機能では対応しきれない恐れがあります。
また、定期的にシステムの仕様がアップデートされる可能性があるため、変更に対応しながら運用を続けていく体制を整えることも大切です。
オフライン環境では利用できなくなる
インターネット環境が必須なため、災害による通信障害やネット環境の不備などオフライン環境では、販売管理システムへのアクセスができず、業務が一時的にストップするリスクがあります。
例えば、受注登録や在庫確認、納品処理などが行えない状態が発生すると、業務全体に大きな支障をきたす可能性も。特に店舗や倉庫、営業先などネット環境が不安定な場所では、取引機会の損失や納期遅延などのリスクにもつながります。
災害時のバックアップ体制や復旧時間の目安、障害発生時の連絡・対応フローについて、事前にベンダーと取り決めておくことで、万が一の際の混乱を最小限に抑えることができます。
セキュリティの強度はベンダーに依存する
クラウド環境のセキュリティは、システム提供ベンダーの技術力や運用体制に大きく依存します。
クラウド上に保管される業務データや顧客情報が外部からの不正アクセスやサイバー攻撃の対象となるリスクがあるため、導入に際しては慎重なチェックが必要です。
通信の暗号化やアクセス制御、多要素認証の有無など、ベンダーがどこまで安全対策を講じているかを事前に確認しましょう。
また、情報漏洩などのトラブルが起きた際の対応フローやサポート体制も、契約前にしっかり把握しておくことが大切です。
ランニングコストがかかる
クラウド型は月額課金制が主流であり、利用期間中は継続的に支払いが発生します。これは初期費用を抑えつつ、いつでも最新機能を使えるという利点もあります。
ただし、利用規模が拡大するにつれ、ユーザー数や機能の追加に応じて月額料金が増加することが多く、結果としてオンプレミス型よりも長期的には費用総額が高くなる場合もあります。
そのため、導入前には初年度だけでなく3年後・5年後といったスパンでのトータルコストを試算し、自社の成長戦略や予算に応じた最適なプラン設計が不可欠です。
システム導入のメリット・デメリットについては、下記のコラムもご覧ください。
クラウド型販売管理システムなら近畿システムサービス
近畿システムサービスでは、クラウド型の販売管理システムを提供しています。東芝テック製のPOSシステムと連動し、商品データや売上の受信をスムーズにおこなうことができるのが特長です。
現在POSシステムのみを導入している店舗でも、簡単に販売管理システムを追加導入することが可能です。
また、多種多様な売上分析帳票を搭載しており、店舗全体の売上はもちろん、部門単位・単品単位のABC分析なども細かく対応。分析結果はPDFやCSV形式で出力可能なため、他のソフトとの連携も簡単です。
こうした機能により、リアルタイムな経営判断や業務の可視化が可能となり、店舗運営の質を大きく向上させます。
近畿システムサービスの販売管理システムについては、こちらのコラムも参考にご覧ください。
クラウド型販売管理システムの導入をご検討の方は、ぜひお気軽にお問い合わせフォームから資料請求をお申し込みください。
まとめ
クラウド型販売管理システムは、売上・在庫・購買を一元管理できる強力なツールです。業務効率の向上、人為的ミスの削減、低コスト・高アクセス性など、多くのメリットがある一方で、セキュリティの強度やカスタマイズの制限など事前に注意しておきたい点も存在します。
導入を検討する際は、自社の業務フローや成長戦略に合わせた製品選びが重要です。最終的には、機能性とサポート体制のバランスを見極め、信頼できるベンダーを選ぶことが成功のカギとなるでしょう。